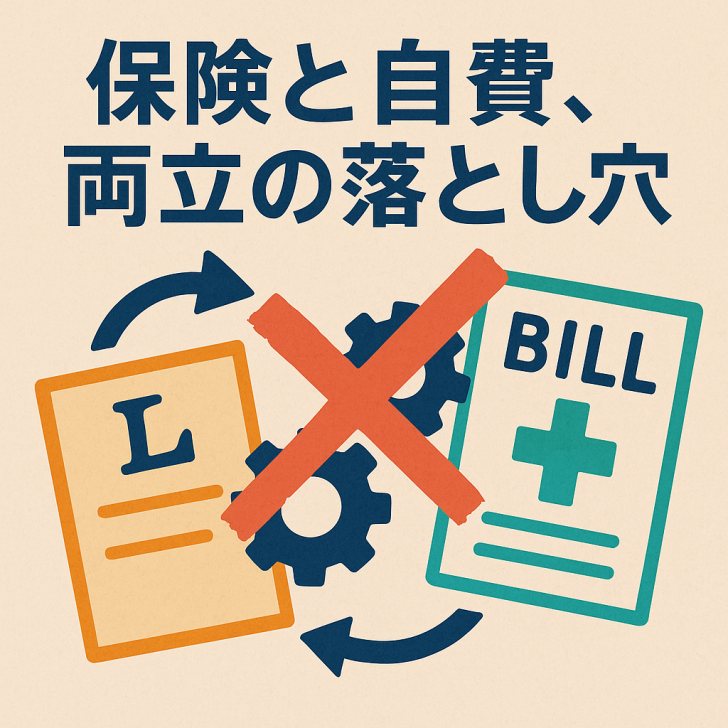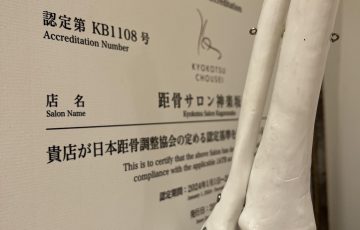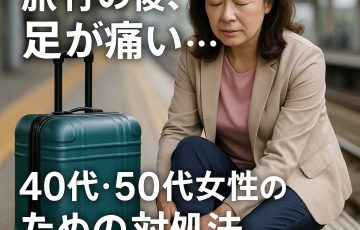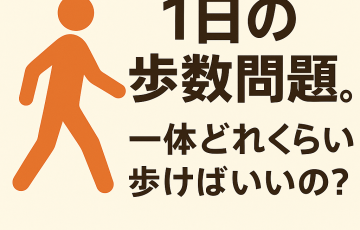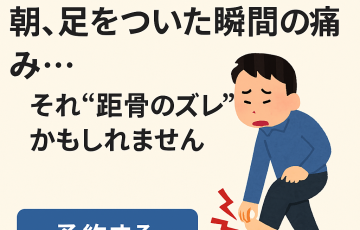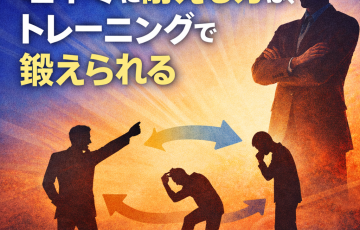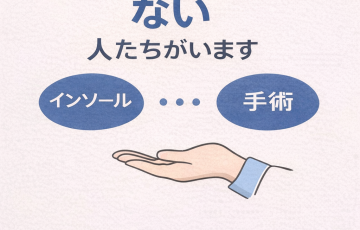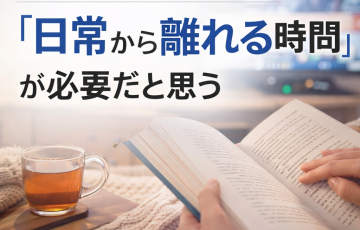さいしょに
整骨院や整体院を経営していると、「保険も使いながら、自費診療も伸ばしたい」という発想は自然です。
一見するとリスク分散のように見えますが、実際に両方を同じ院で同時に回そうとすると“噛み合いの悪さ”を感じるケースが多いのです。
今回は、その理由を整理してみます。
1. 患者さんの意識ギャップ
保険診療は「安く受けられるもの」という意識が強く、自費診療は「質にお金を払うもの」という価値観が求められます。
『安いから来ている』という方も少なからずいらっしゃいます
同じ院内で両方を扱うと「なぜこちらは保険が効いて安いのに、あちらは高額なのか?」という疑問が生まれ、説明や納得に余計なエネルギーを割くことになります。
2. 提供する側のモード切り替え
保険診療は、ルールに基づいた限られた範囲で効率よく施術することが基本です。
一方、自費診療は制約が少なく、時間をかけて深く施術するスタイルが中心。
施術者自身が「スピーディーに数をこなす」モードと「じっくり成果を出す」モードを行き来しなければならず、集中しづらいのが現実です。
3. 経営面でのブレ
保険診療は安定するけれど単価が低く、自費診療は単価が高いが波がある。
両方を追いかけると、結局どちらにも振り切れず「この院は何を強みにしているのか」が患者さんに伝わりにくくなります。
基本的に『薄利多売』の経営手法になります
4. スタッフ教育の複雑化
保険診療では請求ルール遵守や記録管理が必須。
自費診療ではサービス力や接客力、販売スキルが問われます。
両方を同じ院で走らせると教育方針が二重化し、スタッフが混乱しやすくなります。
解決の方向性
- 院ごとに役割を分ける:保険中心の院と、自費専門の院を分ける。
- メニューの線引きを明確に:保険は急性外傷、自費は根本改善やパフォーマンス向上と整理。
- スタッフの適性で担当を分ける:保険請求が得意な人、自費に強い人で棲み分け。
まとめ
保険請求と自費診療は、どちらも強みがあります。
しかし“同時に同じ院で強く回そうとする”と噛み合いづらいのも事実です。
経営者としては「どちらを主軸に据えるのか」を決め、場合によっては分院やメニュー構成で住み分ける方が、結果的に患者さんにもスタッフにもわかりやすく、院の成長スピードも上がっていきます。