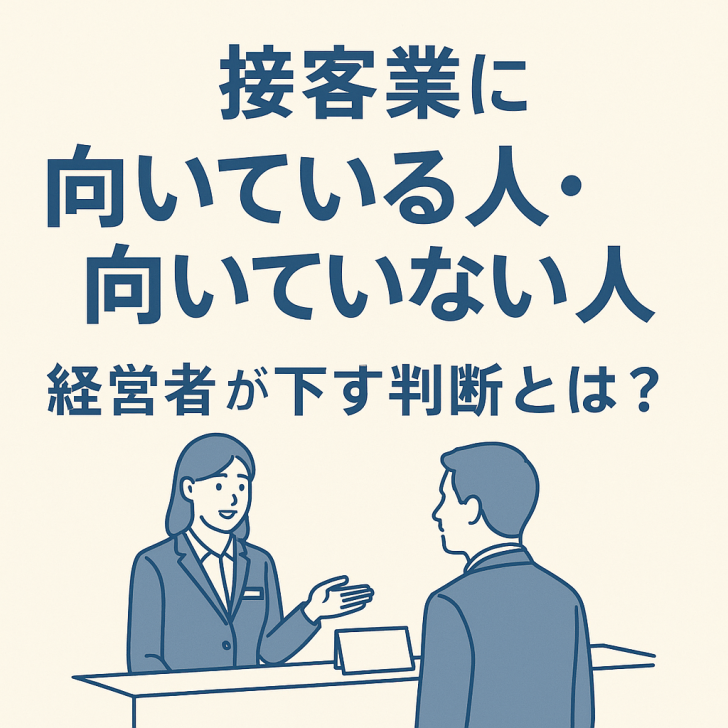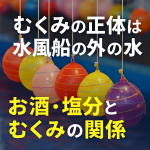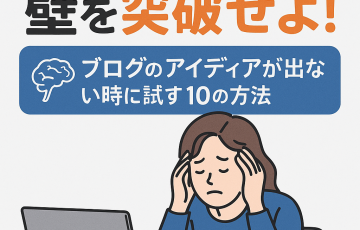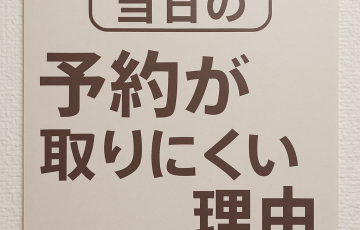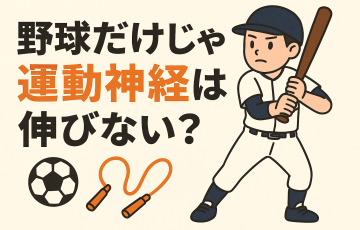接客業に向いている人・向いていない人の境界線とは?
接客業は「人と接すること」が仕事の中心です。
明るい笑顔、安心感を与える声かけ、ちょっとした気配り。こうした積み重ねが、お客様に「また来たい」と思っていただける理由になります。
しかし現実には、どんなに技術や経験があっても 接客自体に向いていない人 も存在します。
経営者としては「努力で改善できる部分」と「どうしても変わらない部分」を見極めることが非常に大切です。
努力で改善できる部分
- 声のトーンや表情
- 言葉遣いや挨拶の仕方
- お客様への姿勢(誠実さ、丁寧さ)
- 緊張のコントロール
これらは練習や経験を積むことで、多くの人が成長できます。実際にスタッフに改善の機会を与えることで、大きく変わるケースも少なくありません。
それでも変わらない場合
一方で、何度改善のチャンスを与えても、なかなか変わらないケースもあります。
例えば…
- お客様との会話がスムーズに成立しない
- 接客そのものに強いストレスを感じている
- 一生懸命やっても現場での評価が変わらない
こうした場合は「本人が悪い」というより 仕事の性質と本人の適性が合っていない と考えるべきです。
経営者としての判断
大切なのは、スタッフを「否定すること」ではありません。
- 「この仕事の性質に合わなかった」
- 「違う環境ならもっと力を発揮できる」
そう伝えることで、本人も次のステージへ進むきっかけになります。
経営者としては 改善の機会を与えた上で、それでも変わらない場合は退職を勧める という判断が必要になることもあります。
それは決して冷たい対応ではなく、本人にとっても会社にとっても前向きな選択です。
まとめ
接客業は「人と人との相性」が大きく影響する仕事です。
努力で伸びる部分もあれば、どうしても変わらない部分もあります。
だからこそ経営者は、スタッフの努力を見守りつつ、冷静に適性を判断する視点を持つことが大切です。
そして時には「この仕事にこだわらなくてもいい」と伝える勇気も、経営者に求められるのではないでしょうか。